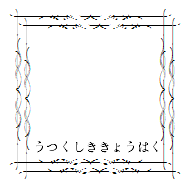 めずらしく、今日は彼と一緒に過ごす土曜日ではなかった。 金曜日、一緒に会社を出て一軒の飲み屋に入った。特別酒が好きではない私はそこまで飲んでいた訳ではなかったが、目の前に座る彼は黄色い液体を喉越しよく流し込んでいた。よくもまあ、それだけ飲めるなと少し呆れてしまう程に。 一緒に彼の家へと帰って、シャワーを浴びて部屋へと戻ったとき彼はまだ飲み足りないと先ほどと同じ液体で喉を潤していた。 「…アル中なの。」 「金曜日くらいいいだろ。も飲むか?」 「ううん。明日予定あるし私はいいや。」 そう言えば、少し残念そうにするのは分かっていたけれど、一週間丸々働いた私の体は疲労の色が濃い。彼は、本当にタフなのだと思う。私の隣のデスクで、毎日遅くまで働いているのを知っているけれど、彼にはその疲れはないのだろうかと不思議に思うくらいに。 酒のつまみとでも言わんばかりに、彼が右手をこちらの方へと振りかざし、私はそれに従う。彼には、きっとまだ寝る気がないのだろう。 白い革製のソファーに腰掛けると、彼は少し動いて私の後ろにその陣を移して、自分自身の定位置とでもいわんばかりにしっくりとした感じで、持っていたビールの缶をテーブルへと置いた。 「左之まだ寝ないの?」 「まだ十一時だぞ。なんだ、眠いのかよ。」 彼に言われて私も時計を見て、まだそんな時間だったのかと思う。いつもであればまだ寝る時間ではなかったけれど、酷く今日は眠い気がしていた。安心できる相手が傍にいるからかもしれないね、なんて言っておけば彼は喜ぶだろうかなんてそんな事を思って言葉を紡げは、その通りの彼のかんばせが映し出された。 私は彼の腕の中で、うつらうつらとソファーで少しばかり気を失いかけていた。普段残業をしない性質だが、今週はよく働いた。充実感に溢れたその疲労に、私はいつの間にか意識を手放していた。 「。」 「うん。十二時になったら、寝る。」 「寝かかっててよく言う。」 「こんな時間に寝たら明日早く起きちゃうし。」 私は目を覚まして、立ち上がる。化粧水を付け忘れたと思い出して、洗面台へと向かってパシャパシャと目を覚ますように肌に叩き込んだ。最早彼の家は、私の家も同然のように必要なものが揃っていた。もし彼が浮気なんてしようものなら、その女が可哀想になるような、そんな部屋だ。 少しだけ覚めた目をこすって、私はリビングに戻る。そうすれば先ほどと同じように手招きをしてくる彼の元に、何の疑い名もなく腰掛けた。 「やっぱり私ももう少しだけ飲もうかな。」 「あんまり飲みすぎるなよ。」 「さっきは自分から勧めてきたくせに。」 「まあ、はザルだしな。」 確かに酒が特別好きなわけではなかったが、私はあまり酒に酔わない。所謂ザルというやつらしい。 彼はコンビニの袋を手繰り寄せて、同じラベルのついた酒を私に手渡してくれた。プルタブを開こうとして、爪をかける。今月はネイルに行けていないせいもあってか、ずいぶんと爪が伸びてしまい上手くそれを開けることが出来なかった。そんな私の葛藤をあざ笑うかのように、缶は取り上げられていとも容易くプシュと音を鳴らして私の元へと帰ってきた。 彼はいつだって、気が回る人間だ。特別、私に対しては格別に。これを幸せと言うのだろうなと思いつつも私は何も言わない。彼も、それに対して開けてやっただろという態度を見せることはない。痒い所に手が届くとはこういう事を言っているのだろうか。 「飲んだら、酔うかな。」 「甘え知らずなには、酔うくらい飲んだ方がちょうどいいかもな。」 「私って、そんなに甘え下手なんだ。知らなかった。」 今まであまり多く付き合ってきた訳ではなかったけれど、その結末は自然消滅が多かった。その結末の所以は、彼が言うように私が甘えないところにあったのかもしれないと今更ながらに思った。甘えると言っても、どう甘えていいのか私にはよく分からなかった。その分、こうして私に必要以上にスキンシップを取ってくれる彼くらいの方が、もしかしたら上手くいくのかもしれない。 既に開いているその缶に口をつける。その液体が喉を通っていく時に何かしらの違和感を体が感じるものの、それは私にたいした酔いを齎さない。 彼とは同じ部署に所属している事もあり、部署の飲み会にも一緒に行くこともあるがこうやって酔えれば楽しいだろうなと考えることもある。彼は酒には滅法強いが、それでもきちんと人並みに酔うらしい。酔っても酔わなくても、基本的な彼のスタンスはいつだってこの現状と変わりないのだけれど。いつだって、甘い言葉と、聞いているこちらが恥ずかしくなるほどの幸せな環境を与えてくれる。そこにアルコールが含まれていても、含まていなかろうとも。ただ、アルコールを含んでいるほうがよりその糖度が高くなるというだけの事だ。 「早く繁忙期終わらないかな。」 「あと一ヶ月もすりゃ落ち着くさ。もっとも、俺は春になればまた新人研修だけどな。」 「左之は一年中忙しいね、ほんと。」 本当に彼は忙しい。上司という訳ではなかったけれど、近い将来彼に用意されているのはそんなポジションなのだろうなと思う。それくらい彼は仕事も出来れば、周りに対する気遣いも出来る。同じ所属の私から見ても、よく分かる事だった。だからこそ、会社とはまるっきり姿を変える彼のそんな姿を、私も特別に愛おしく思う。 彼の開けてくれた缶に二、三度口をつけたがやはり一度眠気を感じのだから再び息を吹き返すことはなく、私は再びうつらうつら宙を舞うように眠気を感じていた。 ベッドから時計を見上げる。時刻は、いつも起きる時間と同じだった。年老いてくると寝る時間が違っても、起きる時間は同じだと聞くが、私もその部類なのだろうか。せっかくの土曜日だというのに、現実は酷く残酷に思えた。 彼に貸してもらっていたスエットを脱いで、自分自身の服を着ようと立ち上がるとその気配に彼は起きたようだった。酷く、寝不足そうなそんなかんばせだった。 「何だ。こんな時間に帰るのかよ。」 「言ったじゃん。今日予定あるって。」 「まだそれまで時間あるだろ。」 彼のいうとおり約束は昼からでまだ時間はあったけれど、家に帰って服を着替えたりと色々あるのだから起こさないまま帰ろうと思っていたのだが、どうやらそれは彼の意に沿わないらしい。 「まだ、行くなよ。」 半分眠りに落ちている彼を振り切るのは簡単だったが、とりあえずもう一度布団へと入る。そうすれば長い腕が伸びてきて、私を包み込む。色っぽい声を紡いだ彼は、もう一歩と、私へと体制を近づけてきて再び眠りへと落ちていった。 どうしようか少し悩んだ後、私も時計を見て再び眠りへと落ちた。 結局私は昼前まで寝てしまい、約束の時間ぎりぎりで目的地へとたどり着いた。一度家に帰ろうとしていたがそんな余裕はなく、彼の部屋にかろうじて置いてあった何着かの服を着て、早々に家に出た。なんなら、一緒に服でも買いに行こうかと言う彼の言葉を、耳から耳へと聞きとおしていくように。 久しぶりに会う友人だったのに、たいした格好も出来ず申し訳なく思っていた所にちょうどその対象となる人物を映し出して、合流した。最初はコーヒーを片手に飲んでいたが、気づいたときには居酒屋で私たちは酒を交わしていた。昼から飲むとなれば、いくらザルと言われる私でもそれなりの酔いを感じていた。遠方から久しぶりに会いに来てくれたその友人との時間は早く過ぎていき、気づいた頃には彼女が自宅へと帰る時間へとなっていた。夜も、更けていた。 昼から飲んでいた私は珍しく酔っていた。全てが面倒に思える。家に帰る道のりが酷く遠く感じる。ふと、彼の家の方が近いことを思い出してスマホを取り出した。 帰るのが面倒だから行ってもいいかと聞けば、彼は二つ返事で了承してくれる。俺に会いたいから来るんじゃないのかなんて言葉も聞こえたけれど、この頭の疼きでそれも耳から耳へと消えていった。 彼は車で向かいに行くつもりだといったが、どうやら酒を既に飲んでしまっていたようだった。電話越しに、聞きなれた笑い声が聞こえた。彼と居るときは、間違いなく飲んでいるに違いないと思ったところでようやくタクシーが一台止まって、私は乗り込み行き先を告げるとすぐに意識を手放した。目を覚まして視界に映ったのは、彼のマンションの前で、彼が私の代わりに代金を払ってくれている姿だった。 柄にもなくふらふらしている私を、彼が脇に固めてエレベーターへと乗り込む。 「お前がこんななるなんて、どんだけ飲んだんだよ。」 「…お昼から飲むと駄目だね。」 「俺とはそんなになるまで飲まないくせに、腹立たしいまでだ。」 エレベータが五階についたと知らせて、私は連れられるように彼の部屋の玄関を数時間ぶりに見た。靴を脱いで、起き直ると再び彼が体を支えてくれてリビングへと戻る。そこには、電話越しでかすかに聞こえた男が確かにいた。 「ちゃんがそんに酔うなんて珍しいな。」 「いや、俺も初めて見た。」 「足がもつれてるじゃねえか。よっぽど飲んだのか。」 「新八に言われてるぞ。いつもの新八みたいだって。」 左之の言葉に、言われた彼は不本意そうにそんな事はないと言い張ったが、いつだって平然としている私を前にすぐにその言葉も止んでいた。私は、相当に酔っているらしい。 彼にソファーに座らされて、水を渡される。蓋が開いているそのペットボトルを口にして、酷く水というだけのそれがおいしく感じられた。やはり自分が酔っ払いであるのだと、私自身もようやく理解に及んでいた。 「普段ちゃんってこんなになるまで飲んだっけか。」 「相当な確立に当たったな、新八。」 水を飲んで少し気分はマシにはなっていたが、それでもまだ疼くように頭が痛い。酒に対してこうも戦いを挑まれるのは久しぶりの事だった。学生以来、こんな事はなかったのだから。 どうやら彼は友人と自宅で飲んでいたらしい。私がそれに水を射してしまった形になる。酷く申し訳ない気持ちに陥りながらも、私にはそんな余裕はなかった。他部署とはいえ、先輩の永倉の事をもてなすどころか彼が私を見ておろおろする始末だ。とんでもなく、情けない。明日になってこの記憶がすべて消えていればいいのにとばかり願った。 「永倉さん、すみません。邪魔してしまって。」 「三人で飲むのもいいかなと思ってたんだが、どうやらそれも無理らしいな。」 「…頭が割れそうです。」 申し訳なさそうに撤退しようとする客人を引きとめ、私のことは気にしないで飲んでくれと告げた。そんな私の言葉を待っていたとでも言わんばかりに彼は悪いなと言って再び目の前の酒へと手をつけた。その光景だけでも、具外の悪い私からすれば酷く辛かった。 ぺちゃくちゃと言葉が時折耳に入った。まだ酒宴は続いているようだった。私は、いつもの白いソファーで左之の方にもたれ掛かるようにして、ぼんやりと二人の事を見ていた。 「あんまりイチャつくなよな。」 「酔ってんだよ。仕方ないだろ。」 「羨ましい限りだぜ。」 「何だ。お前もにもしてやろうか。」 別に甘えている訳ではないのだけれどなと思いながらも、そんな言葉を紡ぐことも阻まれるほどに気持ちが悪かった。自分が酒に強いと過信するのも、今日ばかりで止めにしようと心に誓っていた。 てっぺんを越えた頃、客人はようやく帰っていった。そろそろ静かな環境で私を寝かせてやりたいから帰ってくれとほぼ強制的に帰らされた彼は聊か腑に落ちていないようだったけれど、同じマンションに住んでいる事もあってか一度それを聞くだけで素直に帰って行った。 「左之、ごめん。私もう寝るし永倉さんの家で飲みなおしてくれば。」 「馬鹿。酔った女残してそんな事出来るほど俺は人でなしじゃねえ。」 「酔っ払いなんて、寝れば治るはずだし。」 私の言葉になど従うはずもなく、彼は私をベッドへと誘導した。そういえば、昨日もこのベッドでこれくらいの時間に寝た気がする。飲み足りない彼に、私は迷惑をかけてばかりだ。少なからず、私がここに来なければ終電など関係のない彼らの酒宴はもう少し続いていただろうに。 「どの道電話するつもりだった。」 「そんな心配される程弱くない。」 「こんなに泥酔しててよく言うぜ。」 そんな彼の言葉に、それももっともだなと思ったのが最後の記憶だった。ベッドの淵で早く寝ろと諭してくれる彼の声を耳に入れて、私は本格的な眠りへと落ちていった。 目が、覚めた。いつもの癖で時計をまず見る。やはりそれは皮肉にも会社に行くときに目覚める時刻と同じだ。隣に存在を感じて、ここが自分の家ではない事に気づく。これは、昨日のデジャヴだろうかとふいに思う。ひとつ違うとすれば、頭を抱えたくなるような二日酔いが伴っている事くらいだろうか。 「起きたのか。」 「うん。死ぬほど頭痛い。」 「そりゃあんだけ泥酔してたからな。当たり前だ。」 もう少し寝たほうがマシになると言って、彼は私を抱き寄せる。ただ自分が寝たいのだろうと思いつつ、私もどうしようもなく響きをあげる頭に観念したように、その腕の中で再び眠りにつくことに専念した。今日は、日曜日だ。何も、こんな時間に起きることはないと言い聞かせて。 昨日のように、私が再び目を覚ましたのは昼前のことだった。隣に、彼の気配はない。どこかに出かけたのだろうかとも思ったが、鼻につくやさしい香りで彼がそれを作っていることに気づいた。 まだ頭が痛い。いつだって左之がこうして朝起きて前日の酒が残っている事に自業自得と思ってはいたが、こうまで辛い事だったとは暫く忘れていたような気がする。 「どうだ、気分は。」 「…頭いたい。」 だろうな、という彼の言葉を聞いて私は再びベッドへと転がった。今日は暫く起き上がれそうにもなかった。二日酔いと言って具合が悪そうにしている彼を遠い目で見ていた自分を、今更ながら恥ずかしく思った。 この酷い頭痛のような二日酔いは明日には治るだろうか。治らなければ、部長である土方に殺されると思って一度背筋を震わした。酒なんて、飲むものではない。明日のことを考えるとより一層頭が痛くなるようだった。 「明日、会社行きたくない。」 「それは言われても俺でもどうにも出来ないな。」 それほどまでに私の気分は絶望だった。どうしようもなく、辛い。いつも彼が煩っているのがこういうことだったのかと思いながら、自分がしてきた非礼をそっと心の中で詫びた。二日酔いは、辛い。 私の隣で機嫌を伺ってくれた彼が、突然傍を離れていく。その匂いの元へと、足を運ぶ。暫くカチャカチャと音を鳴らしていたけれど、静かになった頃合でそれを持って私の前へと姿を現した。 「食わないと二日酔いは治らないからな。」 そう言って、私にそのレンゲを差し出した。さして食欲もなかったけれど、二日酔いの達人である彼の言う事を聞いてみようと思い、私は口を開けた。 「…やさしい味がする。」 「だろ。」 先人の知恵は、こういう所で役に立つのかもしれない。私と付き合う前、彼は永倉にも同じような事をしていたのだろうか。考えると、余計と気持ちが悪くなった。 私は運ばれてくるレンゲに口を開いて、食べ進める。 「左之って、料理も出来るんだね。」 「そりゃ一人で住むようになって長いしな。生きる最低限でしかねえよ。」 彼が作ってくれた粥を食べ終えると、彼は私を持ち上げて地面へと立ちなおさせる。そのまま背中を押されてたどり着いた風呂場で、シャワーを浴びて来いと言われる。私はその言葉のまま、仕切りのカーテンを手繰り寄せて、服を脱いだ後にシャワーを浴びた。これで二日酔いは少しでもマシになるのだろうかと、そんな事を思いながら。 シャワーを終えてリビングに戻ると、待ち構えていたように私の視界いっぱいに大きなバスタオルが覆いかぶさった。わしゃわしゃと私の髪についた水滴を取るように、彼は手を動かした。 「至れり尽くせり。」 「具合の悪い奴は手厚くもてなさなきゃいけないだろ。」 「これくらい一人で出来るよ。」 いいからいいから。そう言って、彼はドライヤーを手に持って、私の髪を乾かした。美容室で以外、そんな経験がないものだから何だか不思議な心地だった。白いソファーの下に敷かれているラグの上に座ると、やさしくドライヤーの風が通り抜けていった。時折、私の髪をなでる彼の手が、くすぐったかった。 髪が乾ききったところで、轟音が鳴り止んだ。仕上げといわんばかりに、私の髪に彼の顔があてがわれた。何をしているのだろうかとも思ったけれど、同じシャンプーでも私がそれを使えば違うもののようなのだとそう言って、暫く彼はそうしていた。私は、酷く甘いロボットでも飼っているのだろうか。 まだ、具合は悪い。酷く頭がガンガンする。暫く酒を飲むことを止めようと思うと彼に言うと、明日にはそんな思いも消えると言って笑われた。私は明日会社で、彼が言うような気持ちに、なれるのだろうか。 いつもであればこの時間彼と来る月曜日に憂鬱を抱きながらも晩酌をしていた時間だったが、今日はそんな気にもならない。決まったように長寿番組の落語が始まったが、私はソファーへとうな垂れていた。 このどうしようもなく辛い現状は変えられないと分かっていたけれど、それでも何かを変えたくて、隣にいる彼の体にもたれ掛かってみた。 「何だよ。甘えてんのか。」 いつだって彼は言う。甘えて欲しいのだと。けれど、私は甘えるのがこの上なく苦手だった。しかし、こんなにも頭が錯乱している状況であれば、それも出来るのかもしれないと思った。 「左之が二日酔いで辛い気持ち分かった気がして。」 「なんだそれ。」 「今度からは二日酔いの左之にもう少し優しくしようと思う。」 そう言えば、期待してるとばかりにしっかりと彼の腕に包まれた。私にとっては当たり前とも言える日常だけれど、きっとこんな日常は望んでも手に入れることなど出来ないくらに、尊いものなのだろうとも分かっていた。世の女子が欲しがり、求めるものだと。私が元々それを持ち合わせているただの幸せな女であるということを、再度認識した。 「これで俺も心置きなく飲めるってもんだな。」 明日会社にいる頃には、私の二日酔いも跡形もなく影を潜めている事だろう。 ♯美しき脅迫 |