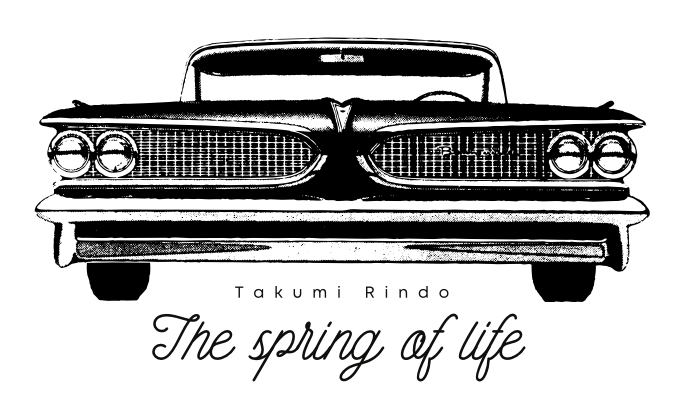 何かを始める時、人はどうやってそれを始めるのか。 簡単なことのように思えて、それは大人になるにつれて分からなくなる気がした。自分の心の内と言動がイコールになる事は年々少なくなってくる。生理現象は仕方がないとして、私が言いたいのはそれ以外の“感情”が伴う事に対してだ。歳をとるごとに感情と言動が逆方向へと独り歩きを始めるように、私の中で一致しない。 「この前こういうのは辞めようって言わなかったか?」 「こういうのって、なに。」 どんどんと自分が冷静になっていって、うまく言葉が紡ぎ出せない息苦しさを感じる。当然の状況で、そして自業自得の状況でもある。 今の私の状況を説明すると、ここは車の中だ。もう少し前の状況へと巻き戻すと、私は今から数十分ほど前までとても楽しく飲んでいた。もっと単純に言えば、愉快に酔っ払っていた。だから、この今へと繋がる状況を思いついたのだ。酔っ払った時だけは“感情”と“言動”が一致する事を利用して。 「もう酔い冷めてるんじゃない?」 彼の言うとおり、私の酔いなんて車に乗る少し前からとっくに冷めていた。物理的に酔いが冷めているのかは分からないが、今この会話の間に心理的な苦しさを感じているのは酔っているからではないというのはよく分かった。 「…言ったと思う。」 「だとしたら懲りないね。」 「そうだね。」 自分の酔いを利用して私が彼を呼び出すのは、これで何度目になるだろうか。玉狛支部で支部長の職についている彼を、私はなんの権限もなく酔っ払っては呼び出した。酔っている時にしか接点を持てない理由は、想像には難くないだろう。 「でもさ、ボスだって呼んだら来るじゃん。」 「犬とかタクシーみたいに言うね、お前。」 「“自分でどうにかしろ”って言わないボスも悪い。」 今日は“ボス”と呼ぶ事に対しての否定はなかった。何度言っても治らない私に呆れて、ついに言うことすら億劫になったのかもしれない。だとすれば、いつまで私はこんな茶番を演じ続けられるだろうか。 大学の卒業を待って、私はボーダーに就職した。防衛隊としての第一線を退き、今までの経験を活かして本部運営の方へと回ったことで、私は長年我が家のように暮らしてきた玉狛支部を出ることとなった。その時から、ボスは私のボスではなくなった。 お前のボスはもう俺じゃないだろと、そう言われる度に複雑な気持ちになった。けれどその一方で、自分のボスという上下しかない関係からも一歩脱却して、進化があるのではないかと思ったのも事実だ。そしてその賭けに出た私は、見事失敗した。僅かに期待していた未来は、何年経っても私の元へはやって来ない。 「俺はお前の保護者じゃないよ?」 「身寄りのない私には似たようなもんでしょ。」 「パパ活ってやつ?」 「パパ活じゃない、たかった事ないし。」 飲み会が終わったタイミングが一番魔が差しやすい。居酒屋の隣に家があれば魔が差すこともないのかもしれないが、生憎繁華街から少し距離のある場所にアパートを借りている私には、その絶妙な距離で必ず魔が差してしまう。自分は酔っているのだと、酔いが半分冷めかかった頭でよく考えもせずにスマホを手に持って、あとは毎回同じ動きだ。 スマホ越しに聞こえてくる感情の読み取りづらいその声に酔いが冷めていくのを感じながら、酔っ払いを演じる私は今日も彼を呼びつけてしまう。来ると、知っているからだ。 「パパになって欲しいわけじゃないよ。」 私の思い描く願望に一ミクロンさえも希望がないのであればスッパリと切り捨ててくれたらいいのに、この男はそれをしない。それが純粋に人としての優しさからくるものなのか、一ミクロン以上は可能性があるのか、後者だと信じたいと願いながらもそんな可能性に縋り付いている自分にもそろそろ疲れてしまった。 「じゃあ何がしたいんだ?」 「それ聞くんだ。」 「まあ、一応ね。確認だよ。」 私の感情や願望なんて言語化しなくても知っているくせにあえて聞いてくるのは、本当に今日こそは私をバッサリと切り捨てる方向へと誘導するための質問なのだろうか。だとすれば、酔っ払いに優しい運転をする彼の車に乗るのも今日が最後になるかもしれない。 「お風呂かご飯か私かどれにする?とか言いたい。」 「願望が旧時代的だな。」 「じゃあ、キスしたい。」 ストレートに言ってみても、結局何も変わらない。別に私に対して焦らしを与えている訳でもなければ、私の気持ちに全く気づいていないという訳でもないのだから何の解決策にもならない。寧ろ彼の言葉に言葉を詰まらせるのは、私の方だ。 「するのは構わないよ。」 「…え?」 「キスする事自体に法的な問題はないだろ。」 言われて、本当に言葉に詰まった。彼が何を言わんとしているのかをなんとなく察知してしまったからだ。酔っているはずの私の脳みそはこれっぽっちも正しい仕事をしてくれない。こういう時、無駄に裏側を読み解こうとしてしまう自分がひどく憎かった。 私の本質的な願望は、キスがしたいという事でもなくて、もっと言うと付き合いたいという訳でもないのだろうと初めて自覚した。 ボスが好きだという気持ちに、ボスからも応えて欲しいというだけのシンプルな答えだ。 「したいなら、しようか?」 なんと答えるのが正解か暫く思案したが、どれも不正解な気がして仕方がない。 ボスは、昔からそうだ。絶対に人に対して自分の立場を利用して命令をする事はしない。いつだって選択肢をいくつか残した状態で、相手にそれを選ばせる。それは一見すると優しい上司のように思えて、実のところその真逆なのだと私は思う。全てを私に委ねて、私に決めさせるのだから。 「なんの罠?」 「別にトラップを仕掛けたつもりはないよ。」 そんなノーリスクで私にとってメリットしかない事が目の前に転がっているのだろうかと考える。どう考えてもそんな旨い話が転がっているとは思えない。やはりこれは何かの終焉へとキスという餌で誘導されているのだろうか。 「聞くくらいならボスからしてよ。」 「中年のおじさんが同意もなしにしたら訴訟もんだ。」 いつになったら南瓜の馬車は姫を迎えにきてくれるのだろうか。いつになったら私は姫になれるのだろうか。そんなおとぎ話のような願望は、一旦捨ててみようと思う。何かを始める時、人は何かを捨てないといけないのだから。 「スリルを得るには多少のリスクを負わないと。」 私はしっかりとリスクを覚悟して、スリルを求めて動き出す。都合よく信号待ちでギアに置かれただけの右手に重心をのせて、期を伺っていると仕掛けてきたのはボスの方からだった。 「で、どんなリスクがあるんだ?」 「意外、興味あるんだね。」 「もちろん、なくはないよ。」 そのリスクを確かめるように、私はもう一度スリルを味わいにいく。それが終わりの始まりなのか、それとも始まらずして終わったのか、私には分からない。今は確かに感じるこのスリルに溺れているので、リスクの方はこの後の私に背負ってもらう事にする。 この際、姫じゃなくてもいいと思う。ロマンティックな馬車が迎えにきてくれなくてもそれでいい。この乗り慣れた車で迎えにきてもらうだけで今の私は満足だ。
容赦のない青春 |