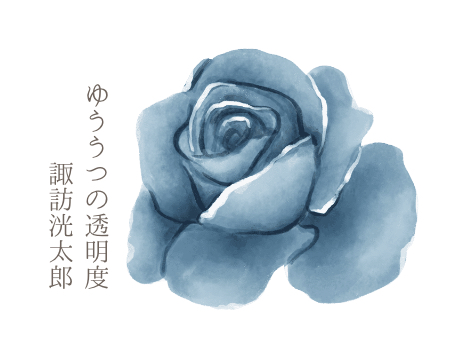 これは私にとっては既に日常になりつつあるが、他人にとってそれは非日常的な内容らしい。無意識に酸素を吸い、二酸化炭素を吐き出すように当たり前で、こんな事を口に出せば相手が驚くかもしれないという概念を失念していた。季節が冬から春に変わり彼が飲んでいるのがホットコーヒーからアイスコーヒーに変わっていて本当によかったと思う。 「諏訪さん、汚い。」 「いや、……お前の口からもっと汚ねえ言葉出てたぞ。」 「え、そう?」 漫画のように綺麗な飛沫をあげて人は飲み物を噴き出せないのだと知る。ぼたぼたと口から吐き出された茶色い液体がテーブルに水溜りを作っていた。せめて彼の口に含まれていたアイスコーヒーが喉を通り切ってから話したほうがよかっただろうか。小首を傾げてそう言おうとしたが、その前に思考を読まれて先周りされてしまう。彼はこういうところで無駄に勘がよく、鋭い。 「今お前が考えてるとこが論点じゃねえ、問題はお前の発言の方だ。」 諏訪さんが一通りツッコミをしたそうだったので、私も万が一を考えて彼が話し終えるまでアイスコーヒーは飲まない。取り敢えず言いたい事は言い終えたらしい諏訪さんは私の返事待ちのターンで、未知の生物を見てくるような眼差しで私を見る。私はそのターンを利用して、アイスコーヒーにストローを差し込んで宙に浮いた氷を溶かしながら、少し薄まったコーヒーで喉を潤す。 「“他人と出したり入れたりするのって浮気なんだっけ”そう言っただけじゃん。」 「あほ!誰が繰り返せって言ったよ、口を慎め。」 諏訪さんはまたアイスコーヒーを吹き出しそうになっていたけれど、学習したのか何かを堪えるようにしてゴクリと大袈裟に音を鳴らせて飲み込んだ。飲み込む学習はしたのかもしれないが、私が再び何か言うかもしれない予想なんて簡単に付くだろうにまた性懲りも無くコーヒーを飲んでいるあたりは学習力に乏しい。いい加減付き合いも長いのだし、私の事をそろそろわかって欲しいものだ。 「…で、全然話が見えねえけど何事だ。」 「自白する必要ないのに何故か浮気自白してきた。」 「それまだ付き合ってんのか。」 「ん、多分付き合ってる。」 「付き合ってる必要あんの?」 「わかんない。でも憎い程じゃないから別れてもない。」 付き合ってからこうして彼に浮気されるのは何度目だろうか。正直もう覚えてられないくらいの日常になりつつあって、両の手の指を使っても追いきれない回数だ。最初の浮気をされた時の私の反応と、今の反応が変わっただけで彼の浮気癖は何も変わらない。 最初のうちは感情のままに泣いて喚いて、手元にあるもの手当たり次第彼に向かって投げつけていたが、回数が右手の指で足りなくなった頃からどんどん感情が露出することがなくなった。それが私の日常になったからだと思う。 「昔はこうじゃなかった筈だけど、もうそれも忘れちゃったんだよね。」 最初は純粋に許せないと感情的にもなったし、浮気された自分を可哀想だと憐れんだ。浮気をされた側にも原因があるなんて言葉があるが、その言葉を考えた人間は碌でもない人間でしかないとそう思った。する側に原因があるだけで、される側に原因等あるはずもない。私は悪くない可哀想と自分で強く念じて誤魔化していたけれど、それが私を追い詰めるように惨めにしていったのかもしれない。そこから、感情的になるのはやめた。 「その年で記憶障害とは難儀なこった。」 「都合悪い所には切り取り線ついてるのかも。」 「図太さが体現されてんな、お前の。」 繰り返されるとわかっている事に一喜一憂していたら肉体も精神も持たず共倒れするのが目に見えていたからきっととても自然にそうなってしまった。私にとっては、自分の考えや体が他の何よりも大事で可愛がるべき対象だ。自分が辛くない方に誘導していく。 こんな事を繰り返されていてもその男が憎くないというのは私の心からの本音だ。理由は先述した通りで、自分が何も感じないように自分の考え方を変えたからだ。憎くはないけれど、好きかと言われたら多分もうその感情もない。だから、許せているのかもしれない。その上で彼と別れないのには、私なりの理由がある。 「出して入れて、何でそれが浮気になるのかな。」 「なら、お前にとってそれは何なんだよ。」 「そう言われると困るけど…ただの出し入れかな。」 「収納みたいに言うな。」 途中から本当にその意味がわからなくなった。“食欲・性欲・睡眠欲”が人間の三代欲求と言われるけれど、おそらく“性欲”に特化して言えば女性よりも男性の方が強いだろう。種を残そうとする動物的な本能なのだから仕方がない。 私にとってはその何十倍も何千倍も食欲や睡眠欲の方が大事だ。性欲は我慢できても、一日食事をしない事も、任務で三徹しろと言われても私には出来ない。それは私が女だからであって、男の人にとってはそれと同じくらい性欲は強い衝動があって、そして抑えられないものなのだろう。私が食事や睡眠を妥協できないのだから、性欲だって妥協できないと言うのは理屈として通るだろう。ボーダー隊員ではない彼にとって、ボーダー隊員として任務優先の私ではもの足りないのかもしれない。もしくは、稀に違う段の引き出しに収納をしてみたいのかもしれない。そのどちらかは私には窺い知れないが、正直どちらでも構わない。 「ならお前は他の奴と簡単に出し入れできんのか。」 「うわっ……それセクハラじゃない?」 「散々連発してたお前にだけは言われたくねえよ。」 私の言う“出し入れ”が何故浮気にあたるのだろうかという疑問は持ちつつも、それが世間的に見て倫理観に反するものであるのは当然ながら理解している。世間の目と言うものは想像以上に大事だ。そもそも私にはそんなリスクを冒してまで浮気をしたいと思うほどの性欲は存在しない。腹いせに同じような真似事をすることも考えなかった訳じゃないけれど、自分へのリスクが大きすぎるし私にとって何もメリットがなくて実行しようとはならなかった。 「それはつまり、私の事誘ってる?」 案外自分もそうしてみることで気分が晴れたりするものなのだろうか。一瞬そんな事を考えて見たけれど、気分が晴れる事はまずない。間違いなくない。もしかすると一時的な解放感やスリルを味わうことができるのかもしれないけれど残るのは罪悪感と、あとは 「あほ、どんな脳みそしてんだ。」 「じゃあ、出来るって言ったら諏訪さんする?」 「なんだよ、したいのか。」 「聞いてみただけ、したいとは言ってない。」 「人のことおちょくって楽しいかよ?」 「……思ったよりは楽しくなかった。」 諏訪さんには昔から面倒を見てもらっている。訓練生の時も、同じガンナーとして私が一人前になるまでの技術を装着してくれたのは彼だった。私にとってボーダーでは非常に馴染みの深い人だ。 諏訪さんの事を異性として見るようになったのは、いつの頃からだっただろうか。私はその境界線をはっきりとは覚えていない。一緒にいればこんな憎まれ口や、彼を困らせるような事ばかり言っているけれど、諏訪さんは私にとって精神的な支柱だ。 「これって、浮気かな?」 私の言う“出し入れ”なんかよりも、この感情の方がよほど本質的に言えば浮気なんじゃないだろうか。もう彼に好きという感情がないとしても、だからと言って他に矢印が向いていていい訳ではない。 だったらそんな男との恋人関係を解消すればいいだけだ。けれど、私には勇気がない。もちろん未練や、別れたくないという気持ちがあるからではない。憎しみはないまでも、男の人の色んな部分を彼と付き合ってみてきた私にとって、それは不安でしかない。こんな感情をまた味わうのであれば、恋などしない方が自分にとっても都合がいいのではないだろうか。 「…浮気じゃないだろ、まだ。」 諏訪さんの右手が私の髪を揺らす。普段ガサツなくせに、欲しい時に欲しい事をしてくれる人だから調子が狂う。はっきりと自分で認めたことはないけれど、多分私は諏訪さんのことが好きなのだろう。異性としてみているのではなく、もう既に異性として好きなんだと思う。 ただの面倒見のいい先輩だったはずの諏訪さんは、いつの間にか私の精神的な支えになっていて、つまり私にとってなくてはならない存在になっていた。なって、しまった。 私は、それが怖かった。今までの親しい先輩後輩の関係性であれば、私はこのまま諏訪さんの近くにいることがきっと叶うだろう。万が一にもそれが今よりも近い関係性になった時の事を考えると、恐ろしくてその先を私は考えられなくなる。 男女として何かが始まれば、基本的にそれは終わりに向かって走っていく。人生が死に向かって動いているのと同じようなもので、なんでも始まるタイミングで終わりに向かって進行していく。今のこの関係性であれば明確な終わりはないという、そんなぬるま湯に私はずっと足を浸けて抜け出せないでいた。 「じゃあどこからが浮気?」 私のこの感情が浮気ではないというのであれば、私はどこまで浮気をせずにいられるだろうか。始まる前から終わりを恐れる私はその始まりに手を伸ばすこともできず、やっぱり今日も宙ぶらりんのままだ。彼とあえて別れないのは、自分がその終わりに向かっている始まりを始めないためだ。彼と別れない限り、私にはそれを始められない明確な理由ができる。 「ろくでなし男と別れたら教えてやるよ。」 それなのにこの男は、それを見透かしたように私の気持ちを揺らしていく。きっと諏訪さんが今何を思って、どうしようとしているのかなんて私の考えている範疇を超えないだろう。 「今日この後は?」 「もう終わり。防衛任務は昼で終わったし。」 「なら、お前俺の家の風呂止めてこい。止め忘れた。」 「今時“お湯張します”タイプじゃないやつ?」 「ユニットバスなめんな。いいから止めてこいよ。」 諏訪さんがわざわざ風呂の湯を張るような男だろうかという単純な疑問が浮かぶが、そもそもユニットバスの狭苦しいところで湯を張るなんてあまりにも不自然だ。どれだけ風呂好きな女子でもユニットバスに湯を張ることはそうそうないだろうし、極論を言えば風呂好きな人間はユニットバスの物件を選ばない。万が一にも諏訪さんがユニットバスに湯を張るとしてもそれは一体どういう状況なんだろうか。お気に入りの本でも持ち込んで読むのだろうか。否、あの諏訪さんが?ありえない。 「返事は。」 「いや、話のくだり繋がってこない。」 「なら繋げろ。」 「意味わかんない。」 「分かんだろ、家の中が水浸しになる。」 ジーンズに捻じ込まれていた鍵を何度か手でポンポンと遊ばせてから弧を描くようにそれを私の方へと投げつけた。直接手で渡すよりももっと、拒否権がない渡し方だ。 私は多分これからしっかりと蛇口の閉まっているはずのユニットバスを確認しに行って、「お湯なんて出てなかったけど、諏訪さん夢遊病なんじゃないですか?」と言うためだけに彼の家に行くのだろう。そして、その後は私も自分の恋人にとっての裏切り行為をするのかもしれない。 「言いたかねえけど、彼氏もお前から振られるの待ってんだろ。自分が悪者にらねえようにお前から振られて、振られたんじゃ仕方ないって言いたいんだろ。」 この話のくだりで、思い出したように彼の事を出してくる諏訪さんはずるい。唐沢さんが未来の幹部候補として諏訪さんを営業部隊へと引っ張りたいと言っているという信憑性のない噂が実しやかに囁かれているが、それも本当のことなのかもしれない。もし仮にこれが私への交渉なのであれば、この場面で潜在的な部分に触れてリスクを訴求しているのだから。 「その発想はなかった。でもすごいしっくりくる。」 私が彼を利用しているように、彼も私を利用しているのかもしれない。そんな関係性しか構築できない男とまだ付き合っている必要など果たしてあるのだろうか。それが諏訪さんへの自分の気持ちを誤魔化すための隠れ蓑だとしてもだ。もはやその役割すらお役御免なのかもしれない。 「…っていうまあ、なんだ、俺の願望。」 リスクを煽っておいて、最後に落としにかかってくるあたり本当に諏訪さんは唐沢さんに一目置かれる男なのかもしれない。悔しいほどの抜群のタイミングで私の心を擽っていく。 「これ出し入れよりも罪重めな浮気じゃないかな。」 もうはっきりと自覚しているこの気持ちを持ったまま、彼の家に上がってもいいものだろうか。その答え次第では、私も新しい一歩を踏み出すことになる。諏訪さんのユニットバスからお湯が溢れていなければ、それが明確に私にとっての動機になるし、同時に諏訪さんから私へのメッセージになるのだから。 「そうかもな。」 一度たりとも否定することなく、あっさりと認めたその言葉を私はどれくらい真面に受け止めればいいのだろうか。こうなれば早く蛇口の行方を見届けて、その答えを擦り合わせたい。 「諏訪さんは重いの背負いたがりだもんね。」 今の私が分かっているのは、諏訪さんは駆け引きに長けていて、そして嘘と恋が下手くそだというちょっと格好の悪い事実と、私自身がこれからするべき行動のみだ。 既に真っ直ぐに向いているであろうこの気持ちは、浮わついてないのだから浮気ではない。けれどそれが本気だと今現時点で認めるのは癪なので、それが本気に変わるかどうかは諏訪さんの腕次第だ。
憂うつの透明度 |