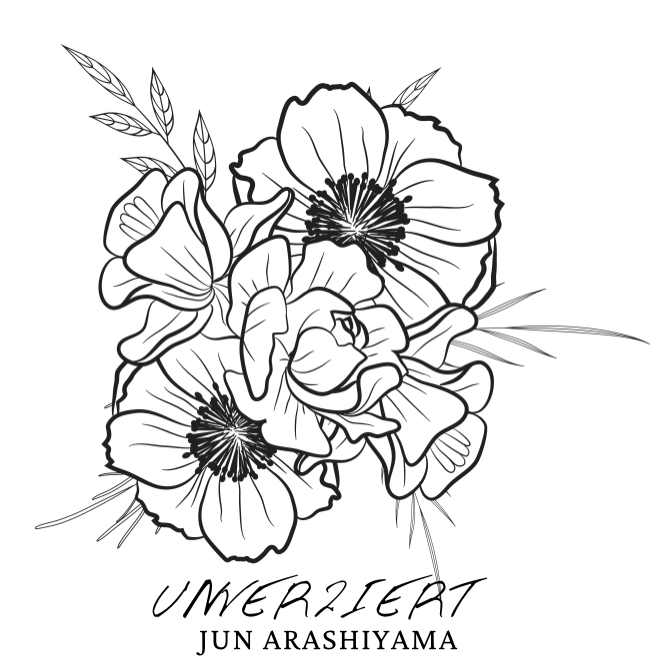 ボーダーに入ったのは、ある意味で生きる手段でしかなかった。別にボーダーに憧れて目指した訳でもないし、正義のヒーローをやりたかった訳でもない。身寄りも家も全てを失った私には、こうするしか生きる術がなかったという、たったそれだけの話だ。 こんな話をすれば悲観して、私を憐れむ人間も多いだろうから、特別誰にも言わずに過ごしてきた。高校を卒業するのと同時に、私は正式にボーダーに就職して、防衛隊から運営本部に転属となった。元々防衛任務がやりたかった訳ではなかったので未練なるものは何もなかった。本部に行きたかったのかと言われたらそうでもないけれど、若い連中の多い防衛隊よりは、居心地がいいのかもしれない。自分の過去や、ボーダーに入った経緯を聞いてくるような連中は、ここにはいない。みんな、割り切った大人しかいない分働きやすさは感じていた。 嵐山とは、本部付になってから話すようになった。元々防衛隊にいた頃から知ってはいたけれど、A級で且つ広報部隊として忙しくしている彼との接点は、あまり多くない。彼と親しくなったのは、私が広報の仕事をするようになってからだ。 広報部隊でも時折夜勤シフトなるものが存在する。広報業務をやりながらも、オペレーターの人数が足りないとなれば、現場にある程度長くいた私はこうして都合よく駆り出される。少し面倒とは思うものの、こうして私の需要がボーダー内である事は決して悪い事ではない。寧ろ、私にとっては都合が良く、防衛隊時代に慣れていた夜勤や無茶なシフトや本来業務との兼業もそこまで苦痛ではなかった。 全ての任務がひと段落して、ゆっくりと寝ている時にスマホがブルブルと音を立てて、何か新しい指令でも入ったのかとベッドから起き上がると、私を気遣う思いやりのある嵐山のメッセージが目に入った。きっと私は間違いなく幸せものだなと、どこかそんな自分を俯瞰してしまう。 “連勤お疲れ様。お疲れの所申し訳ないんだが、今日少し時間取れないか“ ここ最近は本来業務から少し離れていた事もあって、嵐山とはあまり会えていない。きっとどこからか、私が今日久々のオフだと聞きつけて、連絡をしてきたのだろうと思う。本来であれば私から本人に伝えるべきなのに、それに対しても彼は文句を言わず、私を労いながらも声をかけてくれる。私が心地いいと感じる距離感のギリギリを、彼は攻めてくる。 もう少し寝たいなとそんな事を思いながら、夜であれば都合がいい事を返信して、私はもう一度ベッドへと身を投げる。すると、すぐにスヌーズ音を響かせたスマホからは、了解と端的な内容が通知されていた。それを見て、私はもう一度眠りについた。 私が目を覚ました時、既にそこには嵐山の姿があって、一気に眠気が覚めたように飛び起きた。きっとあと少し眠れば自然と起きるだろうと、掛けなかったアラームが災いしてしまった。 「おはよう。ぐっすり眠ってるようだったらから合鍵で入ってしまった、すまない。」 「ううん、合鍵渡したの私だし、全然大丈夫。」 ボーダーの一角に設けられた自室は、生活をする場というよりは寝るだけの場所だ。特別家事が苦手という訳でもないけれど、自分一人だけの為に丁寧に行き届いた家事をする気力は起きないし、それに対しても特に何も感じない。人並みには掃除もするけれど、きっと同じ年頃の女子の部屋と比較すると、あまりに殺風景で、そして散らかっているだろうと思う。 「もしかして洗濯してくれた?」 「ああ、溜まっているようだったからな。もしかしてまずかったか。」 「…まずくはないけど、ずぼらで恥ずかしい。」 「はずぼらじゃないだろ。ここ最近忙しくしてたから。」 寝起きがけの私の隣に腰をかけて、にっこりと誰もが安心するような爽やかな笑顔で“えらいよ“とそう言って、私を存分に甘やかしてくれる。嵐山は誰に対しても平等に優しいけれど、こうして特別優しくしてくれる相手が私だけなのだと思うと、なんと贅沢な立ち位置なのだろうかと自分の事ながら、こんな分不相応な幸せを感じてもいいのだろうかと不安なになる。そんな不安を口にすれば彼を困らすだけなので、私はずっとこの分不相応な幸せに不安を感じながら心の内に留めている。 「そうだ、今日は何か急用だった?」 「彼女に会うのに用事は必要なのか。」 「歯の浮くような甘い台詞だね。」 「本音を言ったつもりだけど、中々には手厳しいな。」 彼だって日々忙しくしている筈だし、学業と兼業しながら広報部隊まで勤めているのだからきっと疲れているだろう。ボーダーの顔として知名度が高い分、色々と難儀することもあるだろうに、そんな事を感じさせない程にいつだって彼は元気で、私を支えてくれる。 「ろくなもん食べてないって、沢村さんに聞いたから。」 「そうかな?普通におにぎりとか食べてるよ。」 「それ以外食べてないんじゃ、栄養偏るだろ。」 そう言って、彼は大きな手荷物を持ってきて、書類が散らばっている殺風景なテーブルに沢山の惣菜を並べていく。ずぼらで、自分の事に無頓着な私に喜んで手を焼いてくれる嵐山らしいなと思って、私も少し笑いながら、いつまでも手品のように出てくる惣菜を眺めていた。 「すごい量だね。ブッフェだ。」 「取り敢えず何が好きか分からなかったから全部買ってしまった。」 そこは普通ではないと自覚しているようで、少し罰が悪そうに笑っている彼が愛おしい。嵐山は何をやるにも全力で、そして自分の事を差し置いて相手の事ばかりを考える。そんな嵐山の唯一になれた私は、やっぱり幸せなんだろうとそう思う。 こんな平々凡々でしかない私が、ボーダーの顔である嵐山と付き合うなんて、当時は夢にも思わなかった。付き合ってからも夢なのではないかと思うほどに、私は満たされて、幸せだった。 「准は私を甘やかしすぎだよ。」 「俺がそうしたいと思っても、それは駄目な事なのか。」 「堕落して駄目な人間になっちゃうよ。」 「堕落なんて出来ないくせに、よく言うよ。」 彼はそう言って、私はしっかり仕事をしているといつも評価してくれる。頑張り屋さんだから、と二言目にはそう言って私を甘やかせる。彼に評価されるのはもちろん嬉しいと思う反面、息が詰まるような気がするのだ。 嵐山の彼女として恥じることのない自分を意識的に作り上げることが、苦しい。まだ若いながらもキビキビ働いているのは、私にはこうするしか術がないからしているだけで、もし一般的な家庭環境の娘であれば私はもっと堕落した生活をしていたのだと容易く想像がつく。 ボーダーに入ったことで、この非の打ち所がない恋人を手に入れた私は、その分不相応な幸せに首を絞められているのかもしれない。全力で私を大切にしてくれる彼に対して引け目を感じてしまうのは、きっとそのせいだろう。 「こっちにおいで。」 彼に言われるままにテーブルに付属している椅子に腰掛けると、私が一番最初に口にしようとした惣菜に嵐山の箸が運ばれて、こちらへとやってくる。当たり前のように運ばれてくるそれを雛鳥のように口を開けて、私も待ち構える。何処か素朴で懐かしい味が広がった。 「なんで私が一番食べたいもの、分かったの。」 「俺が一番食べたいものを取っただけだよ。」 「じゃあ、私と准はもしかしたら似てるのかな。」 「そうかも、そうだといいな。」 私は、しっかりと嵐山准の彼女ができているだろうか。こんなに大切にしてくれている見返りを、私は返せているだろうか。いつだって貰ってばかりで、私は苦しくなる。彼に何も返せている気がしないからだ。どうすれば私は彼に相応の見返りを返せるだろうか。何をすれば、それは叶うのだろうか。 「最近よく思うんだ、幸せって怖いなって。」 「詩人だな。」 「今が一番幸せだから、そう思うのかも。」 一番という言葉を安易に使うべきではないけれど、本当に今が一番私が幸せな瞬間なのだと思う。嵐山と付き合い始めてから、私はきっと幸せのピークにいる。拭いきれず、いつまでもしぶとくついて回る不安の正体をなんとなく分かりながらも、私はそれに目を瞑る。 ピークがあれば、必ず落ちていく。体力でも、年齢でも、美貌でも、なんでもピークは決まっている。だから、幸せのピークにいる私はもう落ちるしかないのかと思うと、恐怖でしかなかった。こんなにも幸せなのに、どうして相反する感情を私は飼い慣らしているのだろうか。自分の事ながら不思議でならないけれど、解消法を私は知らない。 「じゃあその記録、更新しないといけないな。」 彼の言葉の通り、そうなのかもしれない。けれど、それは私をより苦しめるかもしれない。幸せになればなるほどに、その後はどうなるのかという恐怖が拭えない。私も、彼も、誰にもその答えはわからない。だから、手探りをしながら私たちはこの幸せに浸りながら、生きていくしかないのだ。 「そうだね。」 曖昧な自分の気持ちを隠すように、ぎゅっと彼の裾を掴んで抱きつくと、大きな腕がしっかりと私を包んでくれて、どうしようもなく安心する。この感情を、なんと表現すればいいのだろうか。答えが分からないまま、私はこの温もりに縋っていく。
贅沢な不幸 |