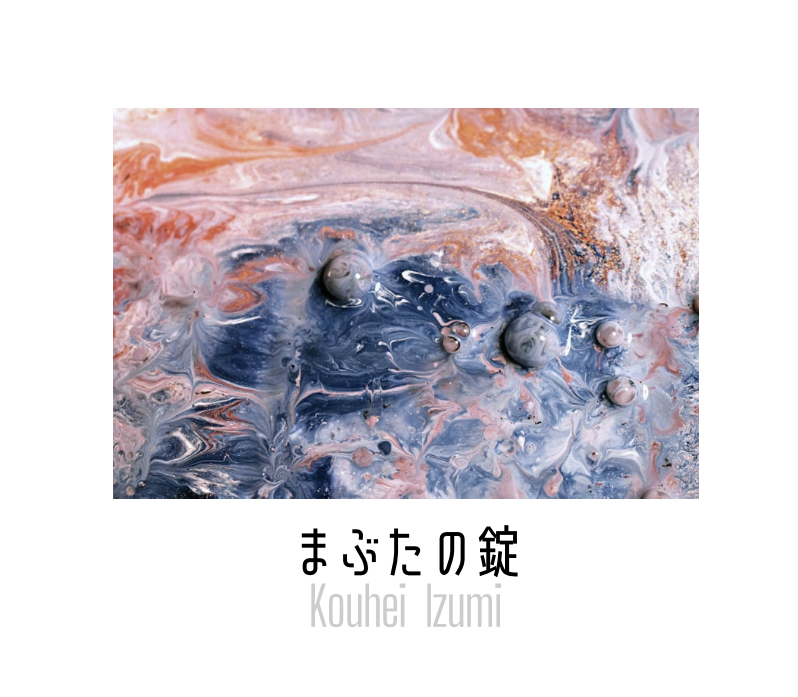 泉じゃなくて、和泉でもなくて、泉水でもない。出水公平は私の恋人だった男だ。 付き合ったきっかけは向こうからのアプローチで、人はこんなにも熱心に自分を売り込むことができるのだなと若干引きながら感心したのを今も鮮明に覚えている。なぜ付き合ったのかと言えば、きっと最初はこんな理由だったのだろうと思う。彼の熱量と勢いに私は押され負けたのだ。それ程に彼の熱意が私に向いているように、あの時の私には見えていたのかもしれない。 「なに、今度は太刀川さんの事好きになっちゃったの?」 そう言って私の様子を楽しげに監視しているのは出水くんだ。彼と付き合っていたのは今は昔の話で、気づけば私も大学で過ごす最後の年になっていた。彼は今年大学二年生になる年で、大手を振ってアルコールが摂取できる大人になる年でもある。 「……私そんな事言ってないよね?」 「太刀川さん卒業して寂しんでしょ?それね、バレバレだから。」 彼はよく私のことを見ていると思う。特に彼が同じ大学へと進学してきてからはより一層だ。けれどきっと、彼は私の真相を知らないのだろうと思う。そして、永遠にその真相に辿り着くことはないのだろうとも思うのだ。 「さんはさ、優柔不断な所あるし流されやすいときた。」 「……なんでそんな事言うの。」 「事実でしょ?それに……」 もう高校生の恋愛ごっこをする年齢じゃない。あの時はそうだったのかもしれないけれど、今は違う。私は明確に恋心を持っているのだ。年下であり、元彼であり、大学の後輩であり、ボーダーの後輩である出水公平に。 「さんがそうやって怯えた顔すると決まって俺ね、ゾクゾクしていじめたくなるの知ってた?」 結局いつもこうだ。 付き合ってばかりの頃は違った。尊いものを扱うように大切にされていたと思うし、彼の言動に初々しさが溢れていた気がする。それもその筈だ。ボーダーでも、学校でも年上の先輩であった私に対して異常なまでの執着を見せてきたのは彼の方だったのだから。 「……やめてよ。」 「本当はやめて欲しくないくせに。」 先輩と後輩という本来の関係性もあって、彼は私に対して所々敬語を使う。一定の距離を置かれているようで、それは私を孤独にさせて不安にもさせる。きっとそれが彼の狙いだと、私自身分かっているのに。自分の感情をコントロールすることができないでいる。 「こうやってね、ちゃんとさんの体も心も理解した上で満たせるのってやっぱ俺しかいないと俺は思うんだけどな。」 いつも思う。会う度に同じような言葉を与えられ続けて、なんと答えるのが正解なのだろうかと。少なくとも分かっているのは、私が望む正解と、彼が私に望む正解が交わらないということだけだ。そんなよく分からない駆け引きをして何年が経ったのだろうか。それは同時に、彼と別れてからの年月が経過している事も物語っている。 「……私を満たしてくれるのは出水くんしかいないけど、出水くんは違うでしょ。」 「へ?」 発展性のないこの関係に疲弊している筈なのに、けれどそれを拒絶する勇気も私にはない。発展性が見えないこの状況下でも、可能性が針の穴先より小さかろうが、結局私はそこにしがみ付くしかないのだ。それが自分を苦しめる地獄となると分かっていたのだとしても。 「どうしたの、さんがそんな事言うの珍しいじゃん。」 「だって事実そうでしょ。」 「それって俺の事大好きって言ってるようなもんだよね?」 否定も肯定もしないで、話は結局私の方へとすり替えられる。だからずるい。その言動は私に希望を見せてはくれない分、絶望の淵に落とし切るほどの決定打もないのだから。首の皮一枚ギリギリで繋がっている状態を、私は継続しているのだ。 「そういうとこ、可愛いなって思うよ俺は。」 「…………」 「あ、でもね?きっと太刀川さんとかは愛が重たい感じとかダルがりそうだよなあ。」 きっと彼が私に執着していた感情、それは恋じゃない。上級生に対する憧れだったり、彼が入る前からA級で着実に実績を出していた私のガワに興味があっただけだ。私自身に興味があった訳じゃない。付き合って暫くしてから、その違和感には気づいていた。 「……て事は結局、さんには俺がぴったりって訳だ。」 想定外だったのは、彼が人の心をコントロールする事に長けていたという事だ。熱意に負けて付き合った、謂わば相思相愛でもなんでもない状態から始まった交際で自分がここまで彼に溺れるとは夢にも思わなかったのだ。 「本当にさんは可愛いなあ。」 きっと太刀川さんに連絡をすれば、彼が動くと思った。それが私の真相であって、私は賭けに出たのだ。太刀川さんに対して特別な感情は何もない。先輩としての尊敬はあっても、異性として色めき立つ感情もなければ、何なら私はそれを利用している卑怯者なのだから。出水公平という男を振り向かせるその為だけに。 「出水くんは全然可愛くない。」 「そう?割と可愛い気はある方だと思うんだけど。」 「私に全然優しくないから。」 「普通に傷つくなあ、こんなに優しくしてるのに。」 そう言って彼は私を包み込むようにベッドで抱きしめる。彼は私のことを可愛いと言ってくれるけれど、好きとは言ってくれない。まるで私の欲しいその唯一の言葉を分かっているかのように。 「でもそれって裏を返せばさ、」 先輩を利用してでもどうしても私が欲しかったのはこんな関係じゃない。フィジカルでは彼を捕えられても、一度だってメンタルで彼を捕えられた事がないのだから。私には彼の心が分からない。付き合ってからも、別れてからも、ずっと分からないままだ。 「優しくない男に毎回抱かれてる訳だからよっぽど相手の事好きじゃないと無理ですよね?」 私が自分以外の人間に興味を抱けば剥き出しの独占欲で自分の方へと向かせるくせに、自分の方を向いた私に彼の興味はないのだ。そんなイタチごっこを続ける地獄から、結局私は抜け出す事が出来ずにこうして今日も彼に抱かれていく。 もう一度彼氏になって欲しい。 そんな願望を毎日募らせている私にはよく分かっている事がある。その言葉を放ってしまえば、今の関係すらなくなるという事を。結局私は自らその地獄に居座っているのかもしれない。 「そうかもしれないね。」 「へえ、最高じゃん。」 何の生産性もないこの行為に、私はいつ終止符を打つ事ができるのだろうか。自らを地獄に陥れる程、私がこの男のことを好きになってしまった事実だけが真実だ。
まぶたの錠 |