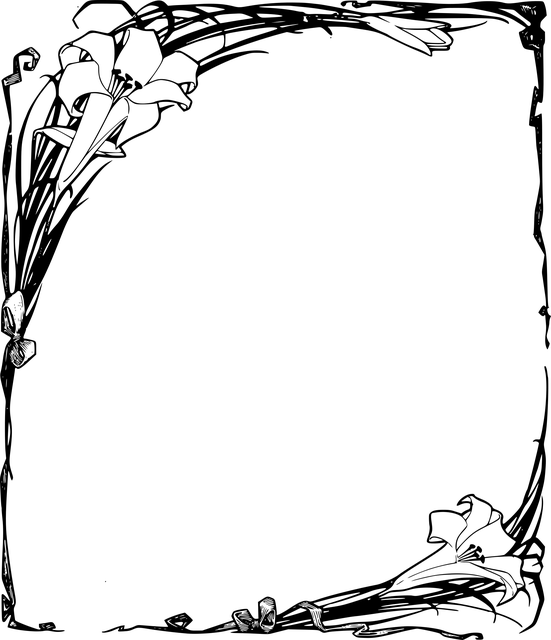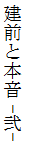初めて伊予を出た私の前には、色々な意味での不思議があった。伊予を出てすぐにどうしようもない田舎道が続いて不安に思うこともあれば、京に入ってからは煌びやかで伊予とは違うと感じさせられるものがあった。見るもの全てが伊予と違って、私にとっては新鮮だった。伊予を出る必要がないとばかり思っていた私は、初めて気づくのだ。私は、伊予に縛り付けられていたのかもしれないと。 京の都はお祭りのような場所だと思った。とても人で賑わっている。私は渡されていた地図と、目的先を探して歩く。予定よりも二日ほど前に京入りできたので、ちょっと観光するのも悪くないと思いつつ今日の宿を探しに向かった。 伊予を出る前、左之の友人から聞いた話だと京はかなり物騒な街らしい。斬りあいだけでなく辻斬りもあると。母親はよくそんなところに娘を単身送り出したなと思いつつ、私はあたりを見渡していた。 新鮮そうなお野菜が売っている八百屋、海が近くないからか魚を置いているところが少ないなと、ふとそんな事を思った。 伊予にいる頃はよく、じゃこ天を作ったものだ。魚の骨ごとすり潰して油で揚げる。皆の好物だった。とりわけ、左之はこれが好きだった事を思い出して、どう表現していいのか分からない感情に陥った。 京で数日過ごせていける金銭と、万が一何かがあった時の小太刀だけを持って京を歩いていた時、私は酷く見覚えのある男を視界に移した。 燃えるように赤い髪を結って、季節問わず軽装な彼をよく知っている。私が知っている頃の彼とは、かなり違うようには見えたけれども、間違いがなくそれは彼だった。 大人になった左之は、どこからどう見ても、魅力的だった。中身はもちろん分からない。彼の表面的な部分を見ただけで彼とは言葉を交わしていないから。でも、きっと精神的にも大人になったんだろうなと嫌でも分かるような彼の姿だった。 浅葱色の羽織を着て立派に隊務をこなしている彼を、暫く遠くから眺めていた。 彼は、京にいた。いつか連れてきてくれると言った、京に。 私はきびつを返す。もっと彼を見ていたいと思う反面、彼の目に触れてはいけないと思った。「左之!」なんて気軽に声をかけられるのであれば、どれだけ楽であっただろうか。彼が私の前から居なくなった事実を考えると、間違ってもそんな事はできなかった。 声をかける事もなく、その赤く燃えるような彼から距離を置いた頃、私は再び宿を探していた。右も左も分からない京の街で戸惑っていた時に、ふと名前を呼ばれた。 「宿探してるんだったら協力するぜ。」 この声を聞いたのは何年ぶりだろうか。いや、八年ぶりに違いない。これは、伊予でいつだって嫌と言っても耳に入ってきた彼の声。不変な彼の声が私の耳に入って、見知らぬ土地でほんの少しの安堵を抱いた。 「なんだ。気づいてたの。」 「最初は目の錯覚かとも思ったけどな。小せえ時から一緒にいたんだ、間違える訳ねえだろ。」 それはこっちの話と、私も同じことを彼に返した。彼が居なくなってから八年。気が遠くなるように長く感じたけれども、実際に彼を前にするとついこの間まで一緒に居たような、そんな気がしてしまう。 「左之、また背のびた?」 「測ってねえけど、もしかしたら伸びたかもな。が前より小さく見える。」 「……なんか腹が立つね。」 そういって、笑った。最後に笑ったのはいつだろうかと考える。昔はよく笑っていた気がする。そこに、私を笑わせてくれる左之がいたから。本当に、久しぶりな気がした。 「その羽織は?」 「ああ、俺は今新撰組にいる。不逞浪士の取り締まり、って感じだな。」 「そう。新撰組って、聞いた事あるよ私も。」 それは伊予を出る前の話。まさか彼が新撰組にるとは思わない彼の友人から聞いた話。京の治安を守る為に設置されたものの、人斬り集団と言われているのだとも聞いた。もちろん目にしないと分からないとは思ったけれれども、今なら言う事ができるだろう。 新撰組は何か信じるものがあって、その隊務を果たしているのだと。 「見ての通り今は隊務中だ。あと少ししたら終わるが、時間あるか。」 「…うん。どこで待ってればいいかな。」 そういうと、彼は彼の隊の列に指差し、私を見た。最初は何を言っているのか分からなかったが、以前聞いた京の状況を思い出して合点がいった。京は危ない街と聞く。左之についていくのが一番の安全策なのかもしれない。それは京にいても、伊予にいても。 私は浅葱色の隊服でぞろぞろ歩く最後列にいた。 京の都がどういうものかも知らない状況で、さらにそこで幼馴染に会い、新撰組と行動を元にしているのだから人生分かったものじゃない。見合いをしにきた京の街で人斬り集団の新撰組に出会い、そこに嘗ての幼馴染がいて、理解が追いつくまでに時間のかかる話だ。 どうしたものかと思っていたところで、屯所につき、他の隊士達は入っていく。ただ、左之は皆を見送ると振り返って私を見て笑った。 「表向き、女とペラペラと話すわけにもいかなくな。」 「……偉い人なんだ、左之。」 「偉いっていう定義が何かって言う事にもよるかもな。」 八年前とは違う、彼を感じた。違和感が残る。とても落ち着いていて、色んな事を悟っていて、私の知らない左之。あのやんちゃだった彼は何処に行ってしまったんだろうか。 「……左之は、変わったね。」 「そうか?自分じゃ分からないからな。」 「変わったよ。ぜんぜん違う。」 「お前だって変わっただろ、。」 そういわれて、あぁ、私は歳を取ったという事に思い出した。彼といた頃よりは老けただろうなと思う。だって彼も、昔とは違うのだから。ただ、彼の場合は老けたのではなく、どうしようもなく男らしくなっていたのだから。 「綺麗になったな。」 びっくりした。伊予にいた頃の彼は絶対にこんな事を言えない男だった。感情のままに動く人ではあったものの、ここまで人の心を左右させる人ではなかった。 「左之は冗談がうまくなったね。…そういえば島原は、行った?」 思っても、気になってもない言葉が口をつく。彼の事だから付き合いで島原に行ったことは間違いなくあるだろう。そこに対しての感想が欲しい訳でもないのに、余計な言葉が口から外へと出て行く。 「また強がりか。」 「何それ。強がってなんか、ない。」 「昔からだがお前の悪い癖だ。」 八年前、私の前から彼が消えてからずっと待っていた。帰ってくるのを。でも彼は帰ってこなかった。少なからずその事に傷ついた。ちょっとしたら頭を掻きながら伊予に戻ってくるんじゃないかと思っていたから。 「久々に会えてよかった。私、もう行くね。」 立派に働いている左之を見るのが辛かった。昔とは違う。もっと背中に色んなものを背負っている彼を見てしまったからこそ自分の出番はないと思うのだ。 京に来たのは左之に会いにくるわけでもないし、そんな事を思う必要もないのだろうけれども。 「なあ。」 「なあに。」 「長くは取らさない。少しだけ俺に時間くれないか。」 そういうと左之は私に確認をとることもせずに、屯所の奥へと行ってしまった。きっと用意をしているのだろう。その間まったく分からないこの屯所で待たされている事に何も思わないのだろうか。 私は屯所の近くにある小石を転がすくらいしか、時間を潰す方法がなかった。 左之を待っている間、誰か来ないかずっと怯えていた。ここは人斬り集団と呼ばれた新撰組の屯所だ。もし誰かに姿を見られたら何が起きてもおかしくはない。そんな恐怖を抱きつつ、私は彼を待っていた。 けれど思いのほか彼は中々やってはこない。私の不安も募った頃、男の声が耳に入った。 「……誰だ。」 酷く警戒している声だった。それもそうか、普通の女であれば新撰組の屯所の前で堂々と待っている事もないだろうから彼らも最悪の事態を想定しているのだろう。 「と申します。」 言ったところで何の意味も持たないとは思ったが、それでも聞かれて名乗らないと斬られると、そう直感的に思った。そもそも言ったところで、私を知る者も居ないのだから名乗ったところで何の支障もないと思った。 「もしかして、あんた伊予の左之の知り合いか?」 左之以上に季節感のない露出感が否めない男だった。名乗った途端、彼は殺気を消してこちらへと進んでくる。 「……知り合いでは、ありますけど。」 そう答えると、彼は完全に緊張を解いて私の隣へとやってくる。これが初対面のはずではあったが、どこかそんな気がしなかった。左之がかつて慕い、一緒にいた兄貴分の彼と雰囲気が似ているように思えた。 「よく聞いた訳じゃないけど名前は聞いてるぜ。あんま、左之の奴言いたがらねえけど。」 「…はあ。そうですか。」 きっと彼は、この京の都でも信頼しえる友を持っているのだろうなと思った。左之のことをこんな風に言う彼は、左之と特別な関係に違いない。何処に行っても、彼は自分の同志を探すのが得意なのだなと、そんな事を思った。 伊予を離れても、彼はちゃんと生きている。私の居ない世界で、ちゃんと大人になっていた。 「おい新八。何勝手な事言ってんだよ。」 「お、左之。俺がお前の可愛い客人を接待してやってたんじゃねえか。」 彼がそう言った後、左之得意の拳が炸裂した。少し向こう側て痛みに悲鳴を上げる彼を見ながら、八年経っても彼の手が出るところは変わっていないと私も可笑しくなって笑ってしまった。 「お前が笑うなよ、。」 「いやだってさ、左之の手が出るところ変わっていないんだと思って。」 「人間そうも簡単に性分や性格変えられねえってこった。」 自分自身で飽きれたように、左之は言う。いつだって私が見ていた彼とは違うように見える彼が、今私の目の前に居る。八年前、私の前から居なくなった左之とはまったく違って見えた。大人びて見える、ではない。彼は、本当に大人になっていた。 「。お前と一緒に行きたい場所がある。」 断る理由もない私は、暗闇がかった京の町を歩く。酷く癖のある道で、伊予とは違うその道でも彼は迷うことなく進んでいる。 そんな事を思った。 どれくらい歩いただろうか。そこまで遠くはなかったけれど、そこまでの道中が二人きりで、お互い柄にもなく沈黙が続いていたから長く感じたのかもしれない。 左之が歩みを止める。続くように私もその場で足を止める。辺りは真っ暗で、何もうかがい知れない。 「今日は月も出てないから見えにくいかもな。」 何故か私の隣にいる彼は、誇らしげにそんな事を言って見せた。私は何の事だがすぐには理解が追いつかない。確かに今日は月がない。あまり視界がよくなかった。 左之は持ってきた提灯に火を付けて、私の周りを明るく灯してくれる。そして、そこで初めて、私は今自分がどこにいるのかを理解した。 「……紅葉。」 見紛うことのない、紅葉。いつだか彼が教えてくれた、それ。言葉で美しいと表現しただけでは安っぽく感じてしまうほどに、立派な光景だった。暗がりの中で照らされた、赤。全てが均一に赤なのではなく、それぞれ個性を出して、集合体として成している。 「連れて行ってやるって、言ったろ。」 「私は一人で京まで来たけどね。」 「あー、確かにな。それは痛いところ突かれた。」 肌寒い風に吹かれて、少しだけ身震いした。彼とこうして紅葉を見上げるのは八年ぶり。私は彼がいなくなってから、八回も一人で色づく赤い葉を見ていたのかと考える。人生五十年と考えると想像していたよりももっと大層で我ながら驚いた。 「ひとつ約束を果たしたところで、だ。」 前置きのようにそう言って、彼は本題を切り出そうとする。 「…京に何しに来たんだ。」 一番聞かれたくも、 一番答えたくもない、核心に触れた
◆建前と本音 -参- |